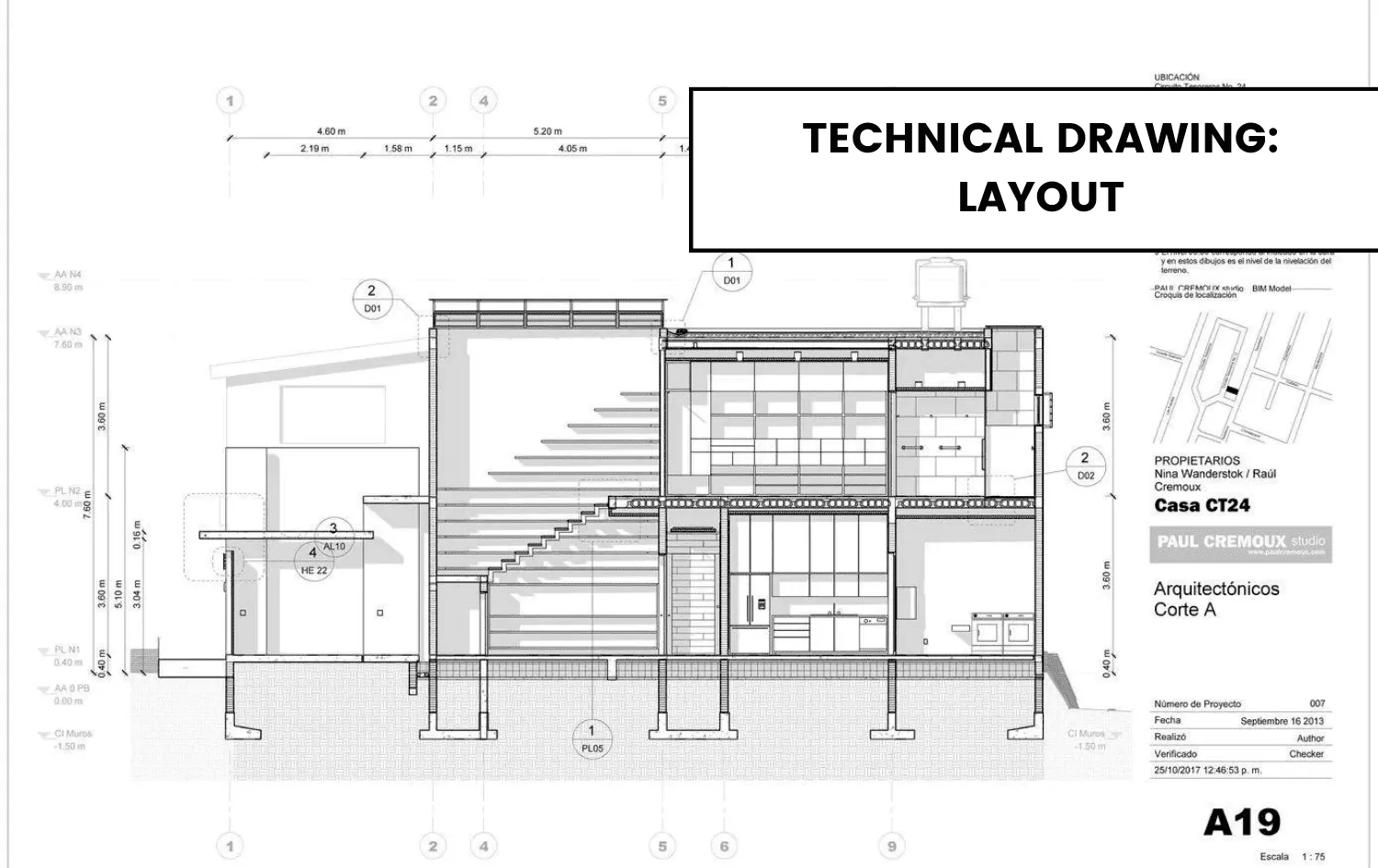従業員保護と持続可能性のための仮設構造物
- 保護エンクロージャー: 仮設通路や頭上の天蓋(足場と一体化していることが多い)は、落下物や天候から作業員を保護する。 これらには、安全規制によって義務付けられている屋根付き足場橋や瓦礫ネットが含まれる。 例えば、英国のクロスレール建設規制では、すべての建設現場は、高さ2.4mの木材の煙突と、公道から後退したゲート付きエントランスで「完全に安全」であることを義務付けている。 米国やEUの同様の規制(足場に関するOSHA 29 CFR 1926、EU-OSHA指令など)は、落下を防止するためのガードレール、手すり、保護デッキを義務付けている。
- 換気と照明: 現場事務所やシェルターは、快適性を高め、エネルギー使用量を削減するため、自然換気、高効率空調、LED照明の設計が増えている。 持ち運び可能なキャビンには、窓、換気口、ミストファンで空気を動かし、半透明のパネルやLEDで明るく低エネルギーの照明をつけることができる。 モジュラー・ユニットの中には、ソーラー・シェーディングや太陽光発電キャノピーを組み込んだものもある。 吸音も気になるところだ。吸音緩衝材として、菌糸体複合パネルのような革新的な素材が提案されている。
- モジュール化と再利用: 現在、多くの仮設構造物は完全にモジュール化されている。 プレハブ・パネル(クロスラミネート材や複合壁パネルなど)は、建設現場の小屋の壁や屋根を形成するもので、後で再利用するために素早く組み立てたり解体したりすることができる。 例えば、「エコ・ランバー」キットは、IKEAスタイルで組み合わされるインターロッキング材や麻石灰材を使用している。 あるシステムでは、1本の丸太から2本のインターロッキング梁を加工し(木材使用量を半減)、運搬時には平らに梱包し、解体時には「リサイクル可能な梱包材以外は何も残さない」と謳っている。 低排出材料(リサイクル・アルミフレーム、麻コンクリートブロック、CLT)の使用は、体積炭素をさらに削減する。

- コンプライアンスと規範: このような介入はすべて、現地の安全基準を満たさなければならない。 米国では、OSHAが足場と足場の強度とガードレールの高さを規定している。 ヨーロッパでは、EN規格や各国のガイドライン(例:ドイツのTRBS規則)が墜落防止システムやデブリネットを要求している。 実際には、これは作業区域の周囲に特定の「アクセス管理区域」を設定することを意味する。 例えば、クロスレールの規制では、作業現場の周囲に車両進入ゲートと恒久的なフェンスを設置することが明確に義務付けられている。 日本も同様に、仮設工事であっても恒久的な工事と同等の堅牢性を確保するため、厳格な安全仕様(ダミー工事のJICA基準など)を定めている。 最初から安全性を組み込むことで、建築家は労働者と環境を同時に保護する仮設シェルターを建設することができる。
空間的エリアプランニング 安全性と効率性
強力な戦略のひとつは、循環を分離することである。 研究や業界の慣行では、重機と歩行者のルートを分離することが強調されている。 請負業者は、人通りの多い歩行者用施設(トレーラー、トイレ、ロッカー)を建物の入り口付近や搬入ゾーンから離れた場所に配置し、機器の通り道を横切らないように明確な歩道を示すことを推奨している。 米国のプロジェクトでは、「各関係者が別々に移動できるように」事前にレイアウトを計画することが多い。 混雑した都市部(ロンドンのクロスレールやニューヨークの高層ビル)では、千鳥配置のアクセスポイントや一方通行のループによって、歩行者ルートにトラックが入り込むのを防いでいる。 また、管理された入場ゲートやカード・アクセスによって、危険区域への入場者を制限することもできる。 まとめると、標識だけでなく物理的なゾーニングを行うことで、作業員と機械を隔離し、安全性と動線を改善することができる。

- 分離された通路: 歩行者用通路が機器レーンと交差しないように敷地を設計する。 バリアやボラードを使用して、保護された歩道を作る。 例えば、大規模な請負業者であれば、建設現場と作業現場を分離するためにバリアを設置し、明確な歩行者ルートを確保することができる。 ボラードやテープで、重機の「進入禁止」区域を指定することもできる。 この空間論理は、頭上エリアにも及ぶ: 足場の通路は、クレーンや配送トラックの足跡の完全に外側に配置することができます。 適切な照明と視覚的な表示(視認性の高いテープ、あるいは高さの低いフェンス)によって、これらの区別を強化します。
- モジュール式フェンスとバリア: 再利用可能なバリケードやスタックを使用して、ゾーンを明確にします。 最新のモジュール式バリアシステムは、軽量のインターロック式アルミまたはプラスチックパネルで構成されています。 固定されているが移動は容易で、現場地図や安全メッセージを表示することができる。 あるメーカーによると、このようなシステムは、プロジェクトを通して繰り返し使用できるように明確に設計されているという。 合板や石膏ボードのバリケードを避けることで、廃棄物を減らすことができる: 「使い捨て材料への依存を減らすことで、モジュール式バリケードは不必要な埋立廃棄物を避けることができます」とサプライヤーは言う。 これらのパネルは、(デジタル印刷で)道案内のためのブランド名を入れたり、リサイクル素材から作ったりすることができるので、安全性と持続可能性を両立させることができる。
- エコな道案内 プラスチック製の標識やバリケードが埋立地に向かう代わりに、多くの現場で環境に優しい代替品が使われている。 例えば、FSC認証の木材やリサイクル・アルミニウムで作られた方向指示標識が一般的になりつつある。 ある看板会社によると、持続可能な看板は木製の土台を使用し、無害なインクを使い、有害なコーティング剤は使用していないという。 スプレーで描かれた足跡やチョークで描かれた矢印(洗い流すと消える)も、プラスチック廃棄物を出さずに流れを誘導することができる。 大規模な都市プロジェクト(クロスレイルや公共交通機関の建設など)では、色分けされたゾーンやラミネート加工された再利用可能な地図を使用することで、使い捨ての標識の必要性を減らすことができる。
- 多目的緩衝ゾーン: 積極的に二重の役割を果たす緩衝地帯を作る。 現場の端に資材置き場を設ければ、隣接する舗装道路を騒音や粉塵から守ることができる。 掘削された瓦礫マウンド(安定化されている場合)は、作業員を風から守ることができる。 暑い現場では、日差しにさらされる作業ゾーンと居住エリアの間に緩衝材としてキャノピーを設置することができる。 このようなマルチユース・プランニング(例えば、営業時間外には倉庫エリアを歩行者の避難場所として利用するなど)は、安全性を高め、生産性を向上させる。
フィールド構造におけるサステイナブル素材
- 竹の足場とパネル アジア太平洋地域では、竹は引き続き仮設建築資材として好まれている。 竹は成長が早く、強度重量比に優れている。 調査によると、竹の足場は、簡単な手工具を使うだけで、鋼鉄の足場の数分の一の時間(~10%)で組み立て・解体できる。 プレハブの竹製「門」フレームやフェンスも、低地の敷地に利用できる。 管理された庭から収穫された竹の足場(および複合竹パネル)は、使い捨ての木材やプラスチックの足場とは異なり、再生可能で生分解性があります。

- 菌糸体コンポジット: キノコの菌糸体シートが断熱材や防音パネルとして登場。 キノコは農業廃棄物で栽培され、乾燥させて硬い形状に加工される。 菌糸体パネルは軽量だが強度があり、耐火性、耐水性、吸音性に優れている。 また、自然に分解されるため、廃棄時に有毒物質を残しません。 建設現場の小屋の壁や天井の被覆材として使用される菌糸体パネルは、機械からの騒音をカットし、作業員が断熱繊維にさらされるのを軽減する。 ある事例(オランダの “グローイング・パビリオン”)では、菌糸体壁がまさにこうした利点を強調している。
- リサイクル金属足場: 従来のスチール製またはアルミ製の足場は、本来リサイクル可能です。 高品質のアルミ製手すりフレームやプレートは、繰り返し溶かすことができます。 実際、リサイクル・アルミニウムは、一次生産エネルギーのわずか5%しか使用していません。 スチールは世界全体で約70%の割合でリサイクルされています。 最新の足場システムは何十年も使用できるように設計されているため、部品はプロジェクトごとに入れ替わります。 ある業界レポートでは、今日の金属製足場は「驚くほど持続可能」であると強調されています。金属製足場は繰り返し組み立て/解体できるように設計されており、使用後は新しい設備にリサイクルできます。 そのため、単発の木製足場よりもはるかに環境に優しい。
- 再生プラスチックとポリマー: 仮設バリアや仮設足場には、再生プラスチックや生分解性プラスチックを使用することができる。 例えば、再生ポリマーを原料とするプラスチック製フェンス基礎が現在販売されており、18kgの基礎は「コンクリートより40%軽い」と謳っており、完全にリサイクル可能である。 消費者使用後のリサイクルHDPEや生分解性混合物から作られたメッシュ・フェンスやネットは、バージン・プラスチックに取って代わることができる。 日よけのキャノピーにも、部分的にバイオ成分を含む布地を使うことができる。 トレンドは、バリア膜に「バイオPE」や堆肥化可能なコーティングを使用することだ。 このような素材は依然として耐候性を提供するが、最終的には土壌を傷つけることなく分解される。
- エコ・ティンバー・キット 革新的な木材製品(多くの場合、麻をベースとする)が、現地でのキャノピーや小屋の建設に使用される。 例えば、麻の技術を使った “iWood “キットは、フラットパック家具と同じように、プロファイルされた木材を連結して使用する。 このシステムは、木材の使用量を半減させ(1本の丸太から2つのピースを製材する)、廃棄物もほとんど出ないと言われている。 また、現地生産と効率的な梱包により、二酸化炭素排出量も非常に少ない。 従来の木造建築とは異なり、このバイオベースのキットは、洗浄すると「リサイクル可能な梱包材以外は何も現場に残さない」。

- ライフサイクルコストと再利用: 竹や菌糸のような「環境にやさしい」素材は、現在では単価が高いものもあるが、廃棄料が安く、再利用の可能性があるため、それを補うことができる。 例えば、モジュール式のフェンス・パネルは、プロジェクト間でレンタル/リースすることで、コストを償却することができる。 ベンダーは、単発の資材を避けることで、所有者は長期的な節約を実現できると指摘する: 「再利用可能なバリケードは、常に新しいバリケードを購入する必要性を減らすことで、長期的な節約を実現します」。 上記の材料(鉄骨足場、アルミフレーム、木製キット)のほとんどは、何十回ものプロジェクトに十分耐えるため、1回あたりの使用コストは非常に低い。 使い捨てのもの(看板など)が残る場合は、再利用可能な基材や透明プラスチック(リサイクル可能)を選択することで、環境フットプリントをさらに最小限に抑えることができます。
気候に影響されやすい休憩場所とシェルター
- 日陰の休憩所: 暑い気候では、雇用主は休憩に日陰を提供すべきである。 OSHAは、労働者に「涼しい場所」を提供することを推奨している。これは、空調の効いたキャラバンや、扇風機や霧吹きを備えたテントでもよい。 業界団体も同様に、現場での大型キャノピーや移動式の「冷却ステーション」を推奨している。 全米CPWRガイドラインによると、高圧ミスト付きテントは、体幹温度を15°F以上下げることができる。 このため、湾岸諸国や南ヨーロッパの現場では、モジュール式の日除け構造、たとえば100%UVカットの生地を使った30×30フィートのポップアップ式キャノピーがよく使われている。 これらは、日差しの変化に応じて移動させることができる。 座席に隣接した携帯用蒸発冷却器(フォッガー)は、キャノピー下の熱ストレスを大幅に軽減する。 冷たい飲料水や電解質飲料を近くにたくさん置いておくことも、暑い地域では標準的な方法である。
- パッシブ冷却設計: 休憩エリアでは、可能な限りパッシブ空調を使用する。 簡単な工夫としては、テントの向きを日差しから離す、緑陰のために仮設の木や棚を植える、明るい色や反射性のある布地を使う、などがある。 砂漠地帯では、伝統的なベドウィンにヒントを得たテント(風通しをよくするためにサイドが長くはためく)も試みられている。 シーリングファン、高い位置にあるルーバー付きの通気口、シェードセイルは、移動式シェルターを最小限のエネルギーで快適にすることができる。 一部の革新的な施設では、流出水を再利用するソーラー式ミストシステムを利用している。 その目的は、休憩中の労働者の体幹温度を低く保つことで、熱中症予防を全体的に改善することです。
- 暖房および防風エリア: 寒冷地では、逆の論理が適用される。 作業員が体を温められるよう、断熱された休憩室や暖房付きのトレーラーが用意される。 請負業者は、避難場所で「ウォームアップ休憩」を取ることを強調している。 テント内の携帯用プロパンや電気ヒーターは、シェルターを氷点下以上に保つことができる。 風の冷たさを軽減するために、開けた場所の周囲に防風壁(仮設の壁や防水シートなど)を設置する。 スカンジナビアやカナダでは、赤外線ヒーター付きの断熱ポリウレタンパネル・シェルター(レンタルされることが多い)が昼食小屋として利用されている。 このような対策は低体温症や凍傷の予防になる。OSHAは、風や寒さが強まるときには休憩を頻繁にとり、寒冷ストレスの兆候について全従業員に再教育することを推奨している。
- 水分補給と文化: 気候への配慮は、水分補給と労働習慣に関連している。 一般的な文化(例:アジアや中東の一部)では、休憩 エリアは共有キッチンや日陰のある大きな広場であるこ とが多く、そこに全員が集まります。 また、アメリカやヨーロッパなどでは、ワーカーは個人用のローリーやキャビンに分散していることもあります。 建築家はどちらの形態にも対応できる: 例えば、グループ休憩用の集中パビリオンを設計したり、マシンヤードの近くに複数の小さな天蓋を設けたりする。 いずれの場合も、クーラーや噴水を適切な場所に設置することで、水を飲むことを奨励している。 ローテク・ソリューションとして、柄杓付きの明るい色の水バケツ(インドで使用)や太陽熱を利用した給水ステーションが、暑い国々で使用されている。 重要なのは、労働者が実際に利用できるよう、快適で見やすく、文化的に適切なヘルプスペースを作ることである。 可搬性に優れ、衝撃の少ない素材(軽量フレーム、ジュートまたはキャンバスの布地)を使用することで、これらのシェルターは重い土台なしでプロジェクト間を移動することができる。
現場安全インフラのための循環型デザイン
現在、多くの企業が現場の安全要素を循環経済の一部として扱っている。 使い捨てのガードレールやスタッキング資材を購入する代わりに、モジュール式キットに投資している。 例えば、請負業者はプロジェクトごとにインターロッキング式金属製ガードレールと足場を発注することができます。 これらのユニットは、OSHAやEUの基準(ガードレールの高さ、耐荷重)を満たし、きれいに解体することができます。 プロジェクトプランナーはまた、BIMモデルや資産データベースに追跡機能を追加する。 これは、各トラックや標識柱に、それが何件のプロジェクトで使用されたかを記録するタグ(通常はバーコード付き)を付けることを意味する。 このようなデジタルの「再利用データ」は、早々に廃棄されるものがないことを保証するのに役立つ。 また、メンテナンスにも役立つ: 50回使用された手すりは、再利用する前に点検と改修のためにオフラインにすることができる。 例えば、スカンスカUKは「リサイクル材料の使用を優先する」と明言しており、コンクリート/木材/金属を現場で分別し、埋め立てではなくリサイクルに回している。

- モジュラー・セーフティ・キット 多くの国際的な建設会社が、プレハブ式の安全システムを開発しています。 これには、取り外し可能なガードレール・アセンブリ(クランプ式金具付きの頑丈なアルミ製または複合製レール)、自立式歩行者バリア、可搬式屋根付き歩道などがあります。 これらは溶接やコンクリートアンカーを使わずに設置されるため、素早く再構成したり、新しいプロジェクトに移動したりすることができます。 構成部品は標準化されているため、A現場の手すりの一部はB現場の規格に適合している。 あるベンダーは、最適化された設計により、「すべての足場フレーム、支柱、板…をさまざまな構成で再利用できる」と述べている。 実際、同じ足場や手すりのプールを複数の作業で循環させることができ、原材料の使用を最小限に抑えることができる。
- 企業の循環型イニシアティブ: 世界的な建設業者は、契約において再利用を義務付けるようになってきている。 例えば、ブイグ社やスカンスカ社は、すべての現場で循環型経済目標を公表している。 当初は解体計画を義務づけ、資材回収の目標を設定している。 スカンスカ社の英国部門は、現場での分別により「コンクリート、木材、金属などの資材は埋立地に送られることなくリサイクルされる」と誇らしげに語っている。 会社によっては、良好な状態で資材を返却したチームに報奨金を出すところもある。 このような方針は、デザインの選択を迫るものである。例えば、標識構造には、使い捨てプラスチックの代わりにアルミニウムのポール(無限にリサイクル可能)を使用することができる。
- デジタルツールの統合: ソフトウェアは偉大な促進剤である。 多くのプロジェクトでは、BIMや資産追跡ツールを使って各仮設要素を記録している。 例えば、現場のデジタルツインにはすべての手すりが含まれ、使用状況と場所を追跡するバーコードやRFIDでタグ付けすることができる。 撤収時には、請負業者が各部品をスキャンして在庫に戻す。 この体系的なアプローチは、部品が廃棄されるのではなく、洗浄や修理のために即座にプログラムされることを意味する。 このようなデータは、入札プロセスにも影響を与えることができる: 新しい工場を計画する際、チームはデータベースからリサイクル品や既存の部品を選択することで、ブランク材の調達を減らすことができる。
- 解体のための設計: 最後に、建築家は初日から解体を想定した計画を立てるべきである。 つまり、混合素材や接着剤でパーツを固定するようなことは避けるということだ。 例えば、モジュール式看板では、接着剤でレイヤーを固定するのではなく、スナップ式のパネルを使用することができます。 手すりは(溶接ではなく)ボルトで固定し、取り外しができるようにする。 一時的な基礎(バラスト・ブロックなど)は、再利用のために現場から運び出すことができるよう、軽量または積み重ね可能なものを選択する。 文書化された解体手順(逆組み立てガイドなど)により、作業員は損傷することなく安全に解体することができる。 こうしたやり方は、廃棄物を最小限に抑える: タイにおける建設現場の慣行を調査したところ、暑さ対策(日除け、クーラー)は計画なしではゴミになることが多いことがわかった。 これとは対照的に、木材やプラスチックを残さない「廃棄物をデザインしない」施設は、循環型アプローチの模範となる。
Dök Architectureをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。