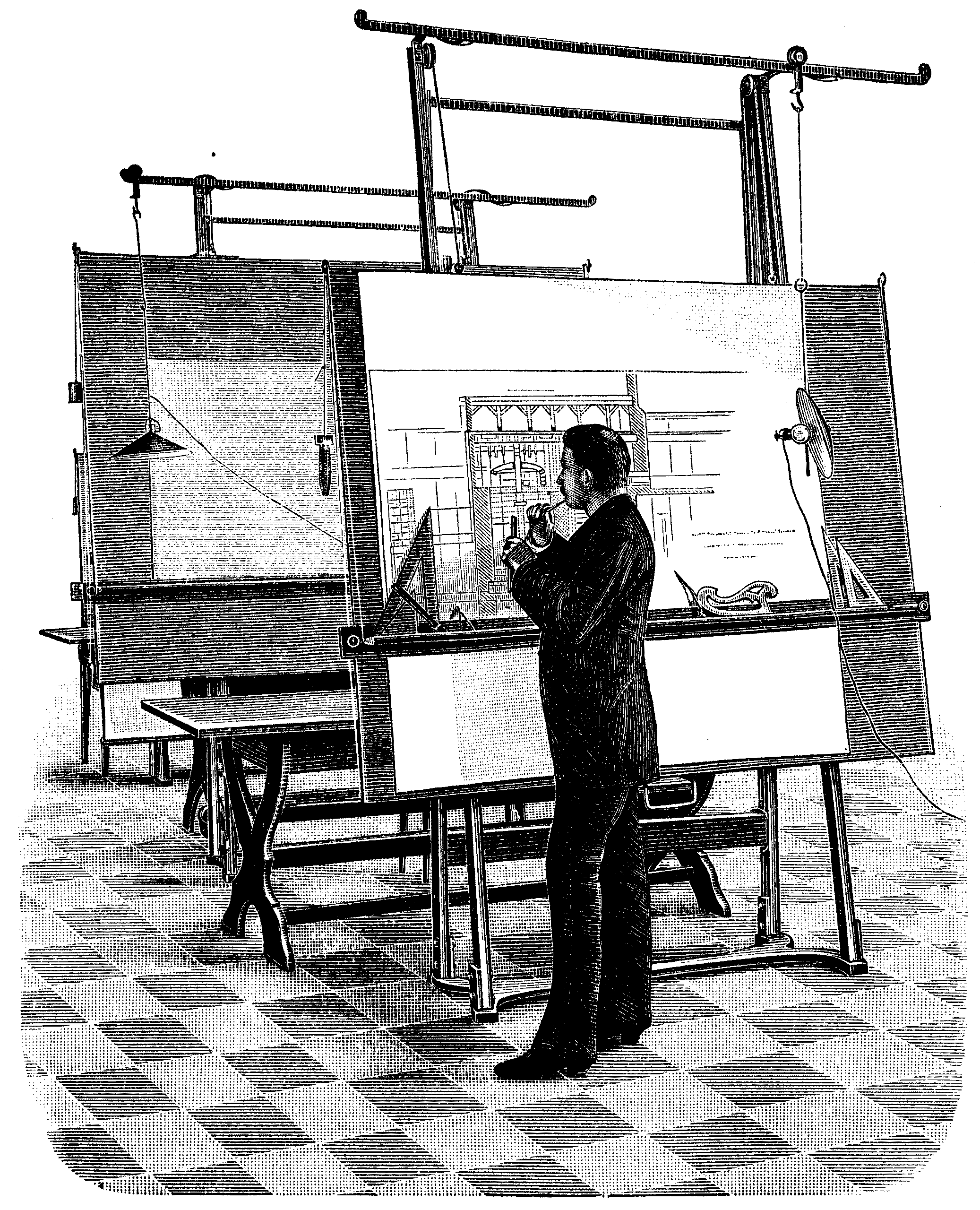完全にユニークな都市
古代の伝説によれば、エフェソス(エフェソス)はアマゾネスとして知られる女戦士たちによって築かれた。 その名は、母なる女神の都市を意味するアルザワ王国の都市アパサスに由来すると考えられている。 この都市に最初に住んだのは、おそらくカリア人とレレグ人であろう。 伝説によれば、アテネの王コドロスの息子アンドロクロスが、神託によって魚とイノシシに導かれ、海に注ぐカイステル川のほとりに2度目の都市を築いたという。 一方、考古学的データによれば、この地域には紀元前2千年紀後半まで先住民が住んでいたという。 この場所は、おそらくヒッタイトの文献に登場するアルザワの首都アパサであり、アヤスルクの丘と同一視できる。 この推測が正しければ、エーゲ海、ミケーネ、クレタからの影響はあまり言及されていないが、ヒッタイト帝国と密接な関係にあった地域大国が存在したと考えられる。 紀元前100年以降、ギリシアの影響が目に見えて増大する。 ギリシアの島々からの最初の植民者は、エーゲ海の東岸、現在イオニアとして知られる地域に定住した可能性が高い。
イオニアの都市は、イオニア人の移住者がエフェソスを中心とする連合に参加した後に発展した。 リディア王の時代、エフェソスは地中海世界で最も裕福な都市のひとつとなった。 リディア王クロイソスがペルシャ王キュロスに敗れたことで、ペルシャの支配がエーゲ海沿岸全域に拡大する道が開かれた。 5世紀初頭、イオニア地方の都市がペルシャに対して蜂起すると、すぐに他の都市から切り離されたため、滅亡を免れた。 エフェソスは、紀元前334年にアレクサンドロス大王が到着するまでペルシアの支配下に置かれ、50年にわたる平和で平穏な時代を迎えた。 リュシマコスは、妻アルシノエにちなんでアルシノエイアと呼ばれる都市の開発に着手した。 彼は新しい港を建設し、パナユルダとビュルビュルダの斜面に防御壁を築き、都市を南西に2.5km移動させた。 紀元前281年、都市はエフェソスとして再興され、地中海で最も重要な商業港のひとつとなった。
紀元前129年、ペルガモンの王アッタロスは、ローマ帝国がこの地域一帯をアジアの属州として併合するために、自らの王国をローマ帝国に遺贈し、ローマ帝国はこの遺言の条件を利用した。
エフェソス市は、アウグストゥス時代以降、非常に重要な貿易拠点となった。 歴史家アエリウス・アリスティデスは、エフェソスはアジアで最も重要な貿易の中心地であったと述べている。 また、エーゲ海で2番目の哲学学校を擁する政治的・知的中心地でもあった。 エフェソスは、東洋と西洋が出会う恵まれた立地と、非常に優れた気候を享受し、アルテミス信仰を持つという重要性も持っていた。 アルテミシオンは、カルト的な重要性とは別に、経済的な役割も担っていた。 銀行、地元で最も重要な地主、難民の避難所という多機能性により、次第に投資対象となった。
1世紀以降、エフェソスにはキリスト教の一神教を広めようとする弟子たちが訪れ、ローマの迫害からの避難を余儀なくされた。 文献によれば、聖パウロは65年から68年までの3年間、この町に滞在し、有名な説教を行い、唯一神信仰を受け入れるよう聴衆に勧めた。 その後1世紀には、福音主義者の聖ヨハネが、彼の守護者である伝説の聖母マリアとともにエフェソスに訪れ、最終的にはアヤスルクの丘に埋葬された。 紀元2世紀には、エフェソスの黄金時代が到来する。 数多くの栄誉ある記念碑が、民間人たちによってエフェソスの人々や市民に贈られた。 エフェソスは、ドミティアヌスを讃える神殿とハドリアヌスを讃える神殿の2つの皇帝崇拝神殿を建てる特権を与えられている。
3世紀、エフェソスとその周辺地域はゴート族によって壊滅的な打撃を受けた。 さらに、西暦270年ごろの大地震によって街全体が破壊された。 当時まだアルテミス信仰が行われていた神殿がゴート族によって破壊されたことと地震は、その後の宗教的発展に深刻な影響を与えた。 神殿は381年まで機能し、崇拝され続けたが、エフェソスの人々は救済に基づく宗教思想に傾倒した。 エジプトの神セラピスやキリスト教のイエス・キリストは、古い公式カルトに代わるものとして、生い茂る人気となった。
西暦380年、皇帝テオドシウス1世のもと、カトリックの信仰が帝国の全住民に課され、異教は「公式に」消滅した。 キリスト教の普及によって高まったこの新しい考え方は、多神教カルトの存在を示すすべての建造物を徐々に放棄し、その代わりにキリスト教会を建設することにつながった。 431年、エフェソスで第3回エキュメニカル公会議が開かれる。 街の中心は旧港周辺に移り、公共建築物や教会、居住区が設けられた。 この地域の生活は14世紀まで続く。 しかし、10世紀の初めには、アヤスルクの丘の頂上周辺に第二のビザンチン集落が形成される。 力関係の変化は11世紀と13世紀に現れる。 1206年以降、ラスカリド王朝の支配下で、初めて長期の平和が実現した。 エフェソス/アヤスルク、あるいはイタリアの資料ではアルタルオゴと呼ばれる集落の中心は、聖ヨハネ大聖堂の周辺にあった。 エフェソスは1304年にトルコに滅ぼされたが、キリスト教巡礼の重要な中心地であり続け、聖地を目指す無数の旅人が訪れた。 経済的な困難にもかかわらず、エフェソス/アヤスルクは重要な交易の中心地であり、地域の海上権力者であり続けた。 エフェソスはまた、アイドゥン王子にとって最も重要な港であり、1348年以降は彼らの帝国の首都となった。 14世紀後半から15世紀初頭にかけては、アイドゥノウル首長国の支配下で最後の繁栄を過ごした。 1402年、ティムール率いるモンゴル軍に攻撃された。 モンゴルが街を去った後、首長国が再興された。 20年間の力関係の後、1425年にオスマン・トルコがこの都市を征服した。 15世紀を通じて繁栄は続いた。 しかし、やがて衰退の一途をたどった。 17世紀には、この廃墟と化した古い大都市にはわずか100人しか住んでおらず、人や動物の間でマラリアが蔓延していた。
20世紀までには、メンデレスが運んだ砂が平野を5キロも広げていた。 エフェソスが放棄され、徐々に衰退し始めた後、かつての壮麗な建造物の廃墟は原材料の供給源となり、それらは解体され、再利用され、再加工された。 近世初期、これらの巨大な遺跡は、旅行記やスケッチにエフェソスやアヤスルクに関する情報を提供し、無数の旅商人のターゲットとなった。 その後何世紀にもわたって、この遺跡は旅行者の記述に頻繁に登場し、主に英仏の資料で紹介された。 ヨーロッパの旅行者は主に古代の遺跡に関心を寄せていたが、トルコの旅行者エヴリヤ・チェレビはトルコの遺跡について最も詳細で優れた記述を残している。
集落の記述
後期古代都市エフェソスの南東に位置するチュクリチ・ホユックは、紀元前7千年紀の先史時代の遺跡を保存している。 この初期の集落は、破壊された後に放棄された。 次にマウンドの使用が確認されたのは紀元前4千年紀半ば、およそ1500年後のことである。 マウンドは、再び放棄された紀元前2500年の初期青銅器時代まで、継続的に居住されていたに違いない。 チュクリチ・ホユックは、エフェソス周辺のみならず、この地域全体で最も古い集落のひとつである。 さらに、アナトリアとエーゲ海の文化圏の交差点に位置することから、エフェソスは、人類先史時代の多くの発展にとって不可欠な、広範な接触と関係を持つことができた。
2008年、パナユルダオの北東テラスで、城壁に囲まれた居住区が発見された。 5棟の住居が部分的に発掘された。 これらは、エフェソスで調査された最初の古典期の住居である。 最も注目すべき発見は、9ヘクタールの居住地域を覆う、部分的に保存状態の良い城塞壁である。 北側のやや急な斜面には、女神メーテルの石造神殿がある。 斜面の北西には港があったと思われ、今でも自然の湾が残っている。 パナユルダにあった古典期からヘレニズム初期の集落は、リュシマホスが都市を築いた紀元前300年頃に破壊され、放棄された。
エフェソスでは、グレコ・ローマ時代のモニュメントや建物がほとんど保存されている。 紀元前300年、リュシマホス王の統治下で、都市はヘレニズム時代の城壁に囲まれた。 城壁は海から東のビュルビュルダまで3kmにわたって続き、特によく守られている。
ヘレニズム時代の都市は、長方形の碁盤目状になっている。 街の上部には、宗教施設や主要な公共・行政モニュメントを含む国家アゴラがあり、下部には大規模な商業市場であるテトラゴノス・アゴラがある。 ヘレニズム時代に遡るが、ローマ帝国時代に全面的に改築された大劇場のような記念碑的建造物もある。 エフェソスの天然の入り江は、2世紀以前にペルガモンのアッタロス2世によって港に改造された。
エフェソスが黄金期を迎えたのは、間違いなくローマ時代、ローマ帝国アジア州の首都であった時代である。 特にアウグストゥス治世に実施された建設計画によって、街の外観は激変した。 エフェソスが普遍的な地中海市場に組み込まれ、外国商人が流入し、高級品への需要が高まったことで、商業活動が飛躍的に増大した。 紀元1世紀の最後の四半世紀、エフェソスの港は小アジアで最も重要な港のひとつに発展した。 六角形の盆地は、船庇、桟橋、倉庫、商店に囲まれていた。 エフェソスの正面入り口にある中央の港の門と巨大な港の浴場は、旅行者が街に入る前に体を洗い、リラックスする機会を提供していた。 港通りの端には、紀元2世紀に最後の増築が行われた大劇場がある。 商業施設や商品は、商業の中心地であるテトラゴノス・アゴラを中心に配置されている。 クレトラー通りには、豪華な装飾が施された住宅、噴水、浴場、ホール、商店、名誉あるモニュメントが並んでいる。 この通りは、紀元2世紀の第一四半期にローマの元老院議員ティによって建設された。 Julius Celsus Polemaeanus、紀元後2世紀第一四半期のローマ元老院議員。 クレトラー通りの西端にあるスロープ・ハウスは、エフェソスに住んでいた上流階級の生活様式を示す傑出した例である。 4000平方メートルに及ぶこの密集住宅地は、ビュルビュルダの北斜面の麓に位置している。 これらの一戸建て住宅は、斜面に2戸ずつのグループで配置されている。 モザイクや壁画、大理石のパネルで装飾されたこれらの家々は、ローマ帝国時代の洗練された上流社会のライフスタイルを物語っている。 ティベリウス治世に建てられた家々は、大地震で倒壊した3世紀まで使われた。
大劇場の巨大な構造は、集落の西側、パナユルダの斜面に面している。 大劇場は、都市の中心地として、また集会の場として機能し、都市のインフラにとって非常に重要であった。 25,000人収容の劇場は帝国時代に完成した。 劇場で行われたのは文化活動だけではない。 この劇場は、剣闘士の試合や、少なくともエクレシアのためにエフェソスの人々が集まる場所でもあった。 この機能は新約聖書にも記されており、聖パウロの宣教に対する銀細工職人たちの反乱について書かれている。 現在の姿は、ローマ時代後期にビザンチン帝国の城壁に接合された際の修復によるところが大きい。
エフェソス大競技場は、街の北側、パナユルダオの北西の突起のふもとにあり、広さは3ヘクタール。 スタジアムの大規模な拡張は、おそらくネロの治世に行われた。 ヴェディウスのギムナジウムはスタジアムの北側にある。 多くのエフェソスのギムナジウムと同様に、浴場とパラエストラ(レスリングや身体訓練が行われたギムナジウムの一部)が東西の経線上に対称的に配置された浴場とギムナジウムの複合施設である。
もうひとつの重要な要素は、ローマ時代のネクロポリスである。 このネクロポリスは、ビュルビュルダの北西斜面、エフェソス港の北と南に位置している。 他のネクロポリスは、パナユルダ(Panayırdağ)の北と東、ビュルビュルダ(Bülbüldağ)の北東斜面、エフェソス上部の町の外側にある。 アゴラは、ヘレニズム時代に建設されたが、アウグストゥスの時代に完全に再建された。 円柱に囲まれたかなり大きな広場の中央には、おそらくデア・ローマ帝国とユリオ=クラウディ帝国の皇帝のひとりに捧げられたと思われる小さな神殿が建てられている。 西の端にはドミティアヌス帝のための神殿があり、北側にはブーレウテリオンやヘスティアイアのあるプリタネイオンなどの公共建築が並んでいる。 南端には、行列用の道路とその他の公共建築物があるが、発掘されたのは代表的な噴水のみで、他は地質学的調査によって判明している。 東側は、ヘレニズム時代後期からビザンチン時代初期にかけての住宅地が広がっている。
エフェソスの街には、さまざまな水道橋によって水が運ばれていた。 このように高度に発達したローマ帝国の建築・土木技術の証は、今でもエフェソス近郊で見ることができる。
街の東、1.5キロのところには、エフェソスの主要な教化の中心地であり、世界の七不思議のひとつでもあるアルテミス神殿(アルテミシオン)がある。 考古学的調査により、紀元前8世紀から古代後期にかけて、この集落に一連の神殿と聖域が存在したことが明らかになっている。 神殿の主な建設段階を2つ挙げておく。 紀元前560年頃、大きな大理石のディプテロス(アルカイック期のアルテミス神殿、ギリシャ建築のランドマーク)の最初の建設工事が始まった。 紀元前356年にアルカイック神殿が破壊された後、118本の柱を持つ新しい神殿が高い基壇の上にそびえ立ち、紀元前4世紀には記念碑的な祭壇が付け加えられた。 アルテミス神殿は、紀元3世紀の地震とゴート族の攻撃によって破壊された。 部分的に再建され、紀元後4世紀後半まで使用された後、解体された。 巨大な大理石の塊は、近くにある聖ヨハネ大聖堂の建設に使われた。
神殿の西約180メートルには、アルテミシオン(神殿を取り囲む聖域)のテメノス(アルテミス神殿周辺の聖域の一部)の建物が見える。 最近の発掘調査によって、この建造物は明らかにオデイオンであり、女神を讃える祭り(アルテミシア)が行われていたことがわかった。 この遺跡の建設は、紀元1世紀後半と推定される。 初期の発掘調査や文献資料から、テメノスは様々な公共建築物や民間建築物で覆われていたことが分かっている。 今日、これらの建造物は何メートルもの土で埋められている。
エフェソスの司教座教会、マリア教会、アヤスルクの洗礼堂と宝物館、記念碑的な聖ヨハネ大聖堂は、エフェソスでよく知られたビザンチン建築の複合施設である。 この複合施設の主要な建物は、ユスティニアヌス帝の治世である西暦6世紀に建設された。 しかし、工事は10世紀から12世紀の中期ビザンチン時代まで続けられた。 マリア教会は、ハドリアヌス帝の皇帝崇拝神殿の南端にある広間に建てられた。 西暦431年の公会議はこの建物で行われた。 司教座聖堂は、4世紀後半から後期ビザンチン時代(14世紀)まで、様々な建築段階を経た。 少なくとも6世紀以降、バシリカはエフェソスの司教座聖堂として機能していた。 中世には教会墓地として使用された。 エフェソスには多くの教会や礼拝堂がある。 地中海世界におけるキリスト教十字架の最も重要な中心地の一つであった。
ビュルビュルダの北斜面にある聖ヨハネの洞窟には、最も素晴らしい壁画がある。 洞窟内には4つの絵が描かれた面があり、1つは他の面の上にある。 洞窟の名前の由来となった場面は西側の壁にあり、側面には聖パウロと聖テクラの伝説を伝えるギリシャ語の碑文が刻まれている。
もう一つの興味深いキリスト教のモニュメントは、パナユルダの西斜面にある七人の眠り人の洞窟です。 この洞窟は、紀元3世紀、自然の岩盤の上にキリスト教の墳墓群が建てられたのが始まりです。 5世紀初頭、皇帝テオドシウス2世の治世に、これらの墓の上に2つの教会が建てられ、ひとつは記念碑的なもの、もうひとつは実用的なものだった。 これらの墓は七人の眠り人のものと考えられ、皇室の命令によってキリスト教カルトが確立された。 七人の眠り姫は復活の模範となり、この教団はテオドシウスの宗教政策における転機と見なされている。 墓地と教会はすぐに巡礼の重要な中心地となり、その役割は中世まで続いた。 この記念碑の人気と名声は、中世を通じて十字軍の碑文にも記されている。
もう一つの重要な地域は、アヤスルクの丘の周辺と西側である。 この集落は14世紀から15世紀、特に中世の主要な発信地であり、アイドゥノグラリ公国、アナトリア・セルジューク帝国、オスマン帝国の過渡期として認識されている。
中世の集落はアヤスルクの丘にあり、要塞に必要な安全も確保されていた。 エフェソス/アヤスルクの最初の拡張は、おそらく14世紀に行われた。 集落の中心は引き続きアクロポリスの丘にあり、市民地域は西側の平野部、古代エフェソスの神聖なアルテミス神殿の上にあったと考えられている。 この集落には、石造りのモニュメントしか残っていない。 薄っぺらな木造建築の住宅は、今日まで残っていない。
アイドゥノウル朝時代の建築計画には、モスク、マスジド、 浴場などが含まれ、それらは元来、都市近隣の住民のため のものであったと思われる。 最も重要な建物は、バシリカの形をした神聖なイサ・ベ イ・モスクです。 この時代、古代とビザンチンの伝統にトルコの革新的な要素を組み合わせた新しい建築秩序が発展した。
世界遺産
トルコ西部のエーゲ海沿岸に横たわる古代都市エフェソスは、新石器時代のチュクリチ・ホユックから中世のアヤスルクまで人が住んでいた。 その長い歴史の中で、ニーズや習慣に合わせて何度も移転してきた。 そのため、約1600ヘクタールにも及ぶこの広大な居住区には、先史時代、アルカイック時代、ヘレニズム時代、ローマ時代、ビザンチン時代、セルジューク時代、アイドゥノウルラール時代、オスマン・トルコ時代、そして現代に至るまで、人類の歴史のあらゆる重要な段階の遺跡が残されています。 どの時代においても、エフェソスはエーゲ海と中央アナトリアとの交易に重要な役割を果たした。 やがてエフェソスは、豊かな天然資源と農業生産のための肥沃な土壌を持つ周辺地域の中心地となった。 エフェソス地域は、歴史的過程を通じて沖積層で徐々に埋められていったため、大きな地層の重なりはなく、さまざまな場所にさまざまな集落が存在している。
ローマ時代と後期アンティークの都市エフェソスは、古代世界の巨大都市の中で唯一、現代に建設されていない都市である。 そのため、エフェソスの遺跡は、古代における都市生活の現象を研究するまたとない機会を提供している。 この驚異的で個性的な証拠の保存は、健全な世界遺産に大きく貢献している。
さらに、エフェソスは宗教史においても傑出した例である。 エフェソスのアルテミス崇拝は、古代世界で最も影響力のある重要なカルトのひとつである。 女神自身は、地中海地域とその向こう(北の辺境まで)全域で崇拝され、巡礼者の群衆がエフェソスの街と最愛の女神の祠を訪れた。 エフェソスには、キリスト教の高官たちが滞在していた(伝説にせよ現実にせよ)ため、古代末期から中世にかけて、この都市は地域を越えた主要な巡礼地となり、現在に至るまで続いている。 最後に、独特の建築コンセプトとビザンチンの伝統を色濃く残すイサ・ベイ・モスクの建設や、エフェソスにおけるイスラム教徒とキリスト教徒の巡礼者の出会いの場も、この集落の特徴である。
エフェソスの特徴のもう一つの例は、港湾地域である。 六角形の防波堤と、隣接する桟橋、船舶用シェルター、倉庫を備えた代表的な列柱通りによって囲まれた港湾盆地には、都市から3つの門が通じている。 紀元2世紀にはすでに、水域は広い水路によって海とつながっていたが、このトンネルは3世紀に狭められた。 運河の両側には、紀元3世紀から5世紀にかけての葬祭用の建造物が並んでいる。 エフェソスのすぐ近くには、運河とクチュク・メンデレス川(キストロス川)に沿って、さらに港があった場所がいくつかある。 これらの建造物は、外港として機能していた。 人工港湾、運河、いくつかの外港、そして隣接するネクロポリスという組み合わせは、古代世界でも類を見ない。
目に見える建築遺構の多くは、その歴史的背景、芸術的職人技、都市の有用性、さらには科学的資源としての潜在的重要性から、他に類を見ないものである。 個々のモニュメントの本質的な価値に加えて、これらの建築物が集合することで、ローマ時代の都市計画が形成され、さらにユニークな歴史的モニュメントであるエフェソスが、トルコや地中海の他の地域では見られない保存状態で、独立した内部地区を形成している。 したがって、エフェソスの考古学的遺跡は、東地中海で最も保存状態の良いローマ時代の建造物が集まっており、あらゆる資産において記念碑的都市であると主張することができる。
Sabine LADSTÄTTER – Lilli ZABRANA
オーストリア考古学研究所
Dark Mode
Light Mode
What are You Looking For?