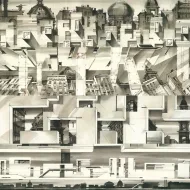旧石器時代から新石器時代にかけて、人間のシェルターは、その土地の状況を直感と 反復学習によって進化してきた。 初期の住居は、煙や熱気を避難させるものだった。道具がなくても、人々は穴を開けたり低い壁を作ったりして、こもった空気を逃がす方法を知っていた。 例えば、暑い気候の地域では風を受けるように家の向きを変え、寒い地域では熱を逃がさないようにコンパクトな形にした。
洪水が起こりやすい地域では高床式の小屋を建て、雨が多い地域では急勾配の茅葺き屋根を建てて保水性を高めた。 厚い石や土の壁などの伝統的な技法は、熱質量(日中は涼しく、夜間は暖かく室内を保つ)を提供し、深い軒やポーチは日陰を提供した。 こうした地域的な戦略は、試行錯誤の末に生まれたものだ: 正式な科学ではなく、地元で蓄積され、世代から世代へと受け継がれてきた知識である。 人類学者は、文化的学習と本能を区別し、ローカルな方法は「世代から世代へと時間をかけて受け継がれ、豊かになっていく」と指摘する。
| 環境/バランス | 建築的対応 | 素材/地域 |
|---|---|---|
| 洪水/湿地 | 杭または杭の上の家屋、地盤を高くしたプラットフォーム | 竹または木材(東南アジア、アマゾン、西アフリカ) |
| 乾燥/砂漠 | 厚い土壁、小さな窓、日陰の中庭;冷房用の風塔 | アドベ/土壁(中東、サハラ砂漠、アメリカ南西部)、白壁(地中海沿岸) |
| 寒冷地/北極圏 | 断熱ドームまたは急勾配の屋根、コンパクトな形状 | 氷のブロック(北極圏のイグルー)、草/石(サーミ、イヌイット、シベリア、北アメリカ) |
| 熱帯雨林 | 軽量フレーム、オープンウォール、ハイルーフ、ベランダ | 茅/竹/木材(太平洋諸島、アマゾンの森、熱帯アジア) |
| 高地/山 | 石壁、勾配屋根(雪用) | 石と木(アンデス、ヒマラヤ、アルプス、モロッコ) |
例えば、西アマゾンの木造マロカやインドの階段井戸、ネパールの石と泥の住居など、これらのモデルは世界的に出現している。 風通しや太陽方位は、その土地の風や太陽の通り道を観察することによって生み出されることが多い。北部の気候では南向きの窓がなく、熱帯地方では風を受けるように居住空間の向きを変える家が多い。 このような解決策は、温度計や設計図が作られるはるか以前から文化的な知識となっていた。コミュニティは、徒弟制度や口頭指導を通じて新しい建築家を教え、設計がいかに伝統として学ばれてきたかを示している。
形と文化を形成する地域の材料
各地域で手に入る建築資材は、その土地の建築の外観と意味を大きく左右してきた。 例えば、成長が早く加工しやすい木材や竹は、アジアの多くの地方建築の基礎を形成している。 実際、7世紀に建てられた法隆寺(木造の塔)は、大工たちが木と職人技に深い敬意を払ってきた文化的背景を反映し、今もなお残っている。 特に竹は、アジアの多くの文化において「日常生活、伝統、精神的な信仰と深く結びついている」ものであり、東南アジア各地の家屋、橋、儀式用の建造物に見られる。 下の写真は現代の例である: インドネシアのバリ島にあるグリーン・スクールのキャンパスは、地元の竹と茅を使って地元の精神で建てられた。

竹や地元の木材のような伝統的な素材は、地元の慣習の連続性を反映した現代的なバナキュラー風のデザインに使用される(ここでは、竹で建てられたバリのグリーン・スクール)。
木材が乏しい乾燥した気候では、土、アドービ、石が主流となる。 マリのモスクからペルーのアンデスの村まで、厚いアドービの壁は永続性と社会的アイデンティティを表現している。 例えば、北米にある多層構造のアドベ・プエブロ(写真はタオス・プエブロ)は、粘土を多く含む土壌が豊富な場所で生まれたもので、その温かみのある茶色の壁は、住民の文化的価値観と一体化している。

複数階建てのタオス・プエブロ(ニューメキシコ州)のようなアドビとアドビのコミュニティは、熱質量と文化的美学(青いドアが象徴的)の両方のために土の素材を使用しており、地元の素材が形態とアイデンティティにどのような影響を与えるかを示している。
石材も同様に建築を形作っている: 南米のインカ神殿からヨーロッパの城に至るまで、石は耐久性とステータスを連想させる。 対照的に、木組みの伝統(スカンジナビアの五線譜の教会、スイスのシャレー、日本の寺院)は、森林環境と関連する儀式(木祭りなど)を反映している。 その他にも、茅葺き、ヤシの葉、小枝編みなど、その土地の素材はそれぞれ地域の特徴を反映している。 パルドが言うように、ヴァナキュラー建築は「地理、入手可能な材料、気候、伝統、文化に深く影響されている」。 こうした材料の選択はまた、文化的儀式(儀式的な家づくりの祭り、木や石に施された象徴的な彫刻など)や美学(色彩、モチーフ)と織り交ぜられているため、その地域の建物は深い文化的意味を持つことになる。
遊牧民と定住民の建築
遊牧民の文化は、絶え間ない移動と風景の変化に適応するため、移動可能な 建築言語を発達させてきた。 例えば、中央アジアのユルト(ゲル)、北米のティピ、北極圏のイグルーでは、折りたたみ可能なフレームと現地の布や革を使い、簡単に荷造りができるようになっている。 遊牧民のテントや宮殿には、持ち運びに便利な家具が備え付けられていることが多い。 モンゴルでは、ユルトのカゴ(カーナ)とフェルトの覆いは、下の写真のように束ねて巻かれている。

モンゴルのフェスティバルで解体されたユルトの部品は、遊牧民のシェルターの可搬性を示している。 このような社会では、「家」は文字通り旅であり、移動のたびに居住空間が設置され、撤去される。
社会学的には、遊牧民の住居は流動的な場所の感覚を促進する。 人類学者のステファニー・カーライルは、遊牧民にとって「『家』は旅と切り離して理解することはできない……空間は移動によって定義される」とまとめている。 彼らの建築は、文字通りこの理念を体現している。建物の形は円形であったり、簡単に組み立てることができたり、コミュニティが移動するたびに家が建て替えられたりする。 カーライルは、遊牧民は「移動に基づくライフスタイルを反映し、促進するために家を建てる……物理的・社会的構造との直接的かつ継続的な相互作用を維持する」と指摘している。 対照的に、定住型の建築(村や都市)は永続性を奨励する。固定された石造りや木造の構造は、長期的なコミットメント、社会的安定、場所の継承を促進する。 このことが心理的に意味するのは、遊牧民は適応性を重んじ、常に変化する空間を共同で共有することを好むのに対し、定住社会は根付き、所有し、ひとつの場所に徐々に伝統を蓄積していくことを重視するということだ。 この違いは、たとえばベドウィンのテントキャンプとアラブの村のムディフ、中央アジアの夏のユルトと冬の石造りの家など、今日でも見ることができる。
近代建築におけるグローバル化と均質化
20世紀以降、グローバルな建築様式がその土地の建築様式を追い越すことが多くなった。 近代的な「国際的」建築物は、ガラス、鉄骨、コンクリートを使った洗練されたミニマルなフォルムが一般的で、このような画一的なアプローチは世界中に広がっている。 ある分析によれば、現代のデベロッパーやグローバル・ブランドは、「 ガラスやスチールといった近代的な素材に支配され……地元の素材や技術を疎外」し、「地元の建築の特徴を消し去る」ような「画一的な」建築アプローチを広めている。 商業ビルのエネルギー使用の70%は空調と照明であるため、ガラス張りのファサードは冷暖房負荷を大幅に増加させる。 多くの新しい開発では、標準的なカーテンウォールや企業のオフィスパークが伝統的な住宅や近隣地域に取って代わり、文化的なまとまりよりもスピードやブランド、効率を優先している。
文化的にも環境的にも、この均質化には犠牲が伴う。 一方では、(ゲーリーのグッゲンハイム・ビルバオのような)象徴的な「スター建築家」プロジェクトは観光を促進してきたが、批評家たちはそれが仰々しく、資源を大量に消費するものだと指摘している。 デザイン界は現在、「より持続可能で文脈に配慮した建物や、仰々しくなく実用的なモニュメント」へと向かっている。 しかし、画一的なグローバル建築は、遺産や場所から人々を切り離しかねない: MDPIの研究者たちは、グローバリゼーションの下で、建築は「特定の文化的・地理的文脈とのつながりを失い始める」と警告している。 急成長する都市は、「環境と無関係」な一般的な開発によって、しばしば地域の居住区を置き換えている。 地域の文化やアイデンティティを脅かす「貧しくなるような画一性」に対する認識が高まっているという調査結果もある。 建設用の鉄鋼、ガラス、コンクリートの生産は、世界の温室効果ガス排出量の約15%を占めており、ガラス張りの巨大構造物が必要とするエネルギーは資源を圧迫している。
地域と持続可能な活性化と壮大さの比較
近年、地元に根ざした持続可能なデザインを目指す 動きが活発化している。 気候変動や文化保護への懸念が、建築家たちに伝統的な原則を学び直させる動機となっている。 ある設計解説にあるように、ヴァナキュラー建築は、持続可能性と文化的アイデンティティへの意識から「今、再生されつつある」。 設計者たちは、地元の材料、パッシブ・ソーラー・デザイン、土着モデルから取り入れた生物気候学的手法を用いるようになってきている。 例えば、ブルキナファソのケレ・アーキテクツ(Kéré Architecture)のような事務所は、地元の土構造建築と現代社会のニーズを融合させ、ベトナムのヴォ・チョン・ギア・アーキテクツは竹構造と自然換気を提唱している。 これらのプロジェクトは(そして世界中の他のプロジェクトも)、高断熱で通気性のある外壁と、慎重に配置された窓や日除けを組み合わせた、「気候変動ヴァナキュラリティ」と呼ぶべきものを特徴としている。
同時に、スピードと魅力が完全に消えたわけではない。 中東の超高層ビルから郊外の広大な複合ビルまで、象徴的な旗艦ビルや急速な都市化プロジェクトによって、多くの国がいまだに地元の風土よりもグローバルな美学を好んでいる。 しかし、国際的な企業であっても、社会的な受容を得るために、その土地に根ざしたものを取り入れたり、その土地に根ざした素材を使ったりすることが多くなっている。 象徴的な超高層ビルや「特徴的な」デザインが依然として広く普及している一方で、文化的な共鳴や環境への回復力を求めて、地域に適合したデザインが再評価される傾向がはっきりと見られる。 社会がグローバリゼーションの文化的・生態学的コストと、地元の知恵に対する再評価を交渉している間、これらの力のバランスは、あらゆる大陸の都市を形成し続けている。